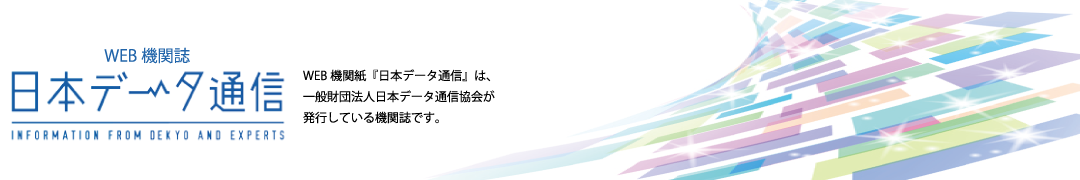自ら学び続ける人材の育成を目指して
山口県立徳山商工高等学校
電子情報技術科教諭 細木 祐吾

学校紹介
本校は、大正8年の開校から様々な変遷を経て、前身となる徳山工業高等学校と徳山商業高等学校が平成18年に再編統合されて設置されました。「誠実」「協働」「実践」の校訓のもと、地域・社会や異なる校種の学校等と連携・協働した教育活動や、「ビジネス教育」と「ものづくり教育」に関する実践的・体験的な教育活動を通して、高度な専門性と豊かな人間性を備え、主体的に地域・社会に貢献し、産業の持続的な発展を担う人材の育成に取り組んでいます。
電子情報技術科について
電子情報技術科では、電気・電子に関する基礎的な知識と技術の習得とともに、高度情報化社会に対応した電気・電子・通信に関する技術者の育成を目指しています。地元に県内最大の周南コンビナートがあり、毎年多くの生徒が化学・鉄鋼・機械メーカーへ就職しています。最近では、システム開発やネットワーク関連など、これまでほとんど求人のなかったIT分野の職種が増え、多様な職業に対応できる人材の育成が求められています。
そこで、座学ではタブレットPCを活用して、C言語やVBAのプログラミングはもちろん、表計算やデータベース、プレゼンテーションも作成し、実践的・体験的な授業に取り組んでいます。実習では、計測や論理回路、電気工事などの基礎分野に加えて、シーケンス制御やネットワーク・サーバ構築、生徒各自で製作したマイコン搭載ロボットを使ったライントレース制御やWi-Fiによる遠隔制御プログラミングを行うことで、電気・電子・情報通信技術分野における幅広い知識・技術の習得に力を入れています。
これらの授業等を通して生徒は専門分野に強く関心を持つようになり、知識・技術をさらに深めるべく、地元の公立大学や工業高等専門学校へ進学・編入学する者もいます。
資格取得への取組み
本科では学年ごとに国家資格の取得目標を定めており、1年次で、地元企業で働くために不可欠な「危険物取扱者(乙種第4類)」、2年次で「第二種電気工事士」、3年次で「工事担任者 第二級デジタル通信」を取得できるよう、関連する授業で生徒のサポートをしています。
以前は、合格者を1名でも多く出すために、授業以外にも早朝課外や放課後の個別指導・補習を行っており、各資格の指導担当教員に非常に多くの時間と労力の負担を強いてきました。しかし、近年の多忙化や人手不足の影響によりその継続が困難になってきており、4年前には3年次の工事担任者試験の資格取得指導を取りやめてしまいました。また、生徒自身も「やらされ感」をもつ者や個別指導をあてにして家庭学習を怠る者が目に付くという有様で、卒業生が入社した企業から「履歴書に様々な取得資格が記載されていたわりには、入社してから必要な資格を取得できない」という声を耳にすることもありました。
この状況を打開するため、結果として合格者数が多少低下しても、生徒に「何のために資格を取るのか」「資格取得を通じて何を身につけたいのか」という質問に対する各自の答えを考えさせることで、明確な目的意識とともに、教員のサポートだけに頼らず家庭学習を中心に自分で学習を進めていく自立意識をもたせることに注力することにしました。入学式の日に生徒だけでなく保護者にも、目先の合格・不合格ではなく「社会に出てから必要なアップデートを生徒自身ができる力をつける」という本科の資格取得指導の意義を理解してもらい、実際の指導においても、家庭学習の成果をマークシートやクラウドサービスで翌日担当教員が効率的に確認し、理解度の低い部分について関連する分野の授業担当教員がそれぞれの授業内で解説や問題演習を行うというサイクルがうまく回るように心がけました。これにより、生徒が個別指導や補習に頼らずに自身で学習を進める意識をもつようになり、以前よりも教員の時間と労力における負担を抑えられてきたように思います。また、電気工事士の技能試験対策として、地元の電気工事会社の協力のもと、生徒が直接技術指導を受けられる講習会を複数回設定し、生徒はもちろん、我々教員も非常に勉強になる機会となりました。心配された試験結果も、以前と変わらない合格者数を確保できました。合格できなかった生徒が再受験する際には、自身で立てた学習プランをもとに家庭学習を進めていけるように、教員がサポートするという形をとりました。
この体制に切り替えた現3年生31名の現時点での資格取得率は、危険物取扱者乙種第4類100%、第二種電気工事士97%、全国工業高等学校長協会情報技術検定2級100%に達することができました。この結果を受けて、一旦やめてしまった工事担任者試験のクラス全員受験を、生徒自身の部活動や進路選択の状況に応じて希望者のみ受験する形に変更しました。試験内容としては1・2年次に履修した科目内容の復習もありますが、3年次のコンピュータシステム技術やハードウェア技術、ソフトウェア技術、通信技術の関連する内容を1学期にまとめて行うことで、試験範囲の大部分を網羅できます。演習問題を家庭学習で行い、要点の再確認や類題の演習・解説などを授業で行うというサイクルを続けました。また、教室の授業ではタブレットPCを使い、実習でもLAN構築・ルーティング実習を取り入れることで、理論だけでなく実践的な知識・技術を習得できるよう工夫しました。試験に向けて、早朝課外も放課後の個別指導・補習も一切行いませんでした。受験を再開した2年前は受験希望者が少数で合格率も以前に比べてかなり低下してしまいましたが、その後受験希望者が増加し、このたび第二級デジタル通信に3年生23名が受験し、19名が合格しました。
今後の課題
これまでの個別指導や補習に頼らずに生徒が自分で学習を進める体制に切り替えていくことにより、生徒の主体性を伸ばしながら、教員の負担を抑えることが少しずつ実現し始めたと感じています。これを持続していくには、結果だけにとらわれず、生徒の自主性を信じ、それを促していくという教員の意識改革と指導スキルの向上が必要であり、これまで以上に科教員の連携が重要となります。時間的・労力的な負担を減らしつつ、若手・ベテランに関係なく、教員自身もアップデートしていける科内の体制づくりに力を入れていき、生徒が社会に出てからも自ら学び続ける力を身につけられる教育の実現を目指していきたいと考えています。

生徒の感想
- 選択科目の通信技術を履修していなかったので、工事担任者試験を受験するのが正直不安でした。しかし、基礎と技術の分野は必須科目の授業と家庭学習で十分合格点に届きそうだったので、法規の分野は自分で計画して勉強を進めました。要点を抑えながら問題演習を繰り返し、わからない部分は友人や先生に聞くなどして、第二級デジタル通信に合格することができました。資格を取得できただけでなく、コンピュータネットワークに関する実用的な知識・技術を身につけることもできたと思います。
- 国家資格は取りたいけれど、3年最後の県高校総体もあるので受験することを迷っていました。CBT試験により都合のよい受験日を設定できることがわかり、大会が終わってから工事担任者第二級デジタル通信の試験を受けることにしました。授業と家庭学習だけで、補習がないのが不安でしたが、無事合格することができました。自分の力で目標に向かって努力することの大切さを学びました。
- 授業で先生の解説を聞き、家では自分のペースで繰り返し問題集を解きました。補習がないので、わからないときは自分から積極的に聞くことと、わずかな空き時間をうまく活用することが大切だと気付きました。また、どのように計画を立てて勉強に取り組むかを自分で考えられるようになったと思います。就職してからも必要な資格をしっかり取っていきたいです。